新NISAの開始でiDeCoの出口戦略はここまで簡略化する

YoutubeやツイッターでNISAやiDeCoを始めることが
常識のように取り扱われていますが
普及率を見ると、焦る必要はありません。
特にiDeCo制度の普及率はまだまだ低く、
NISAだけでいいかと思っている人も多いのでは?
この記事では、新NISAが開始することで
iDeCoにどのように影響するのかを解説します。
本ページはプロモーションが含まれています。
旧NISA制度+iDeCoの場合

現行の旧つみたてNISA制度の場合、
20年の非課税期間が設けられていたため
20年後に株価が暴落した場合、
ダメージを分散できませんでした。
そのため、出口戦略が複雑化して
皆さんもお困りだったのではないでしょうか。
新NISA制度+iDeCoの場合

新NISA制度の場合、
非課税期間が撤廃され、
保持し続ける限り運用益が非課税です。
この場合、出口戦略の自由度が大幅に向上し
iDeCoの出口戦略のみ考えるだけでよくなりました。
新NISA制度+iDeCoのシミュレーション

こちらは一例ですが
30歳~60歳まで月々3万円を投資した場合のシミュレーションです。
(新NISAに2万円、iDeCoに1万円投資)
平均年利は、3%としており
分散性の高い投資信託を選べば、達成可能な範囲です。
【60歳の時の資産状況】
新NISA:11,654,738円
iDeCo : 5,800,340円(退職金控除を利用の場合)
以下が具体的な計算内容です。
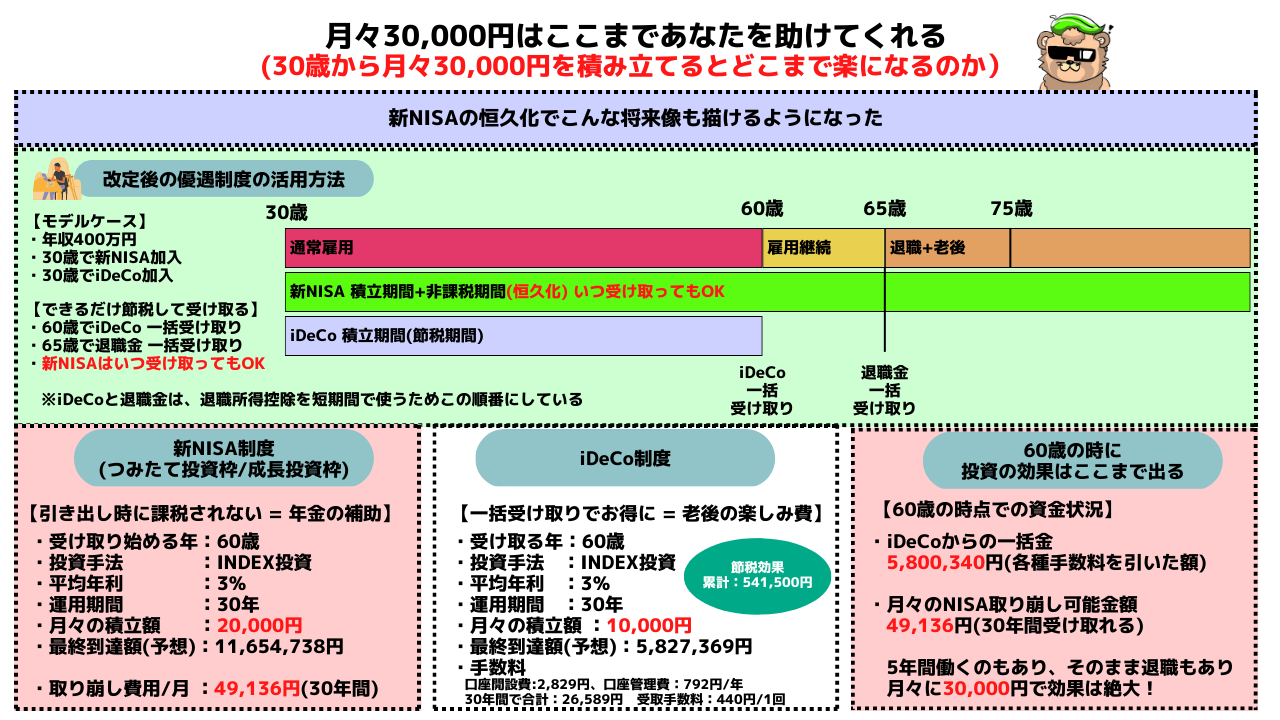
なぜ、iDeCoを併用するのか
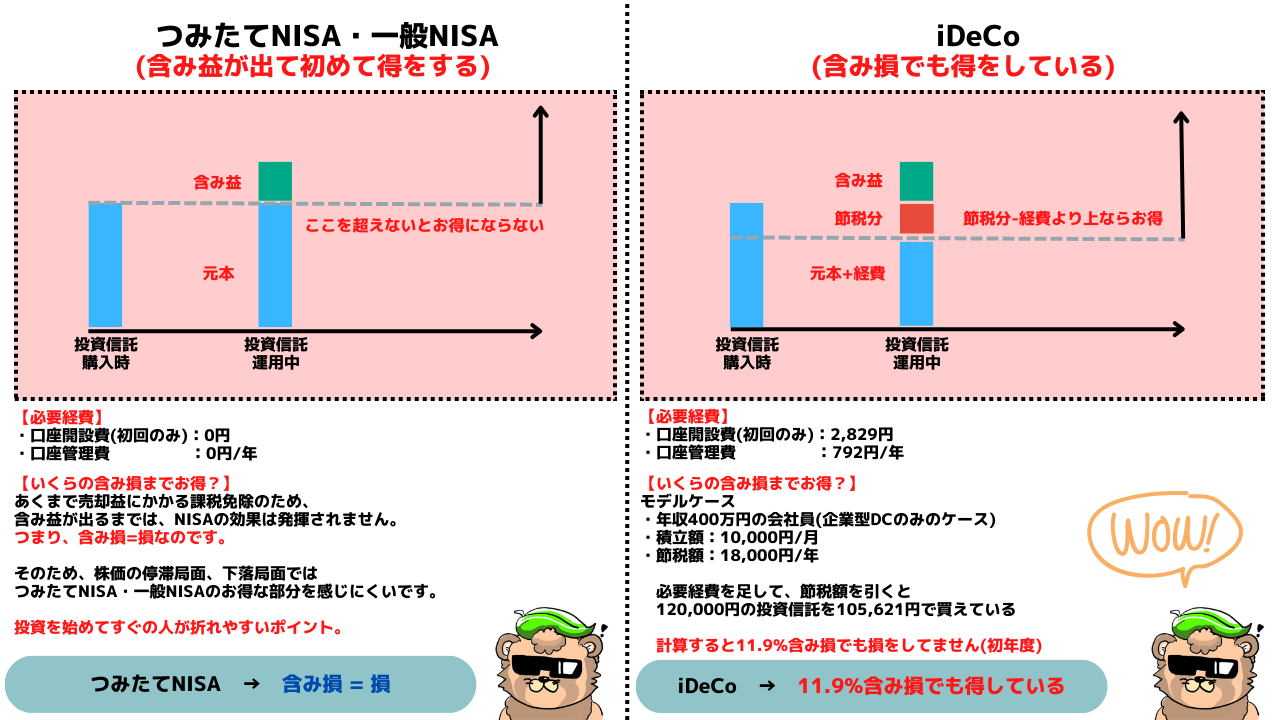
iDeCOは、この図のように
投資額に対して非課税枠が存在します。
例えば、年収400万円の会社員で
企業型DCのみに加入しているケースでは
月1万円をiDeCoで投資すると年18,000円お得に積立られれます。
【実質積立額】
新NISA:120,000円/年
iDeCo : 102,000円/年
いかがでしょうか
これが30年分積みあがると
何と“54万円”もお得に積み立てられます。
▼もし興味が沸いたらこちらのサイトでシミュレーション▼

60歳以降のお得な受け取り方(計算編)
受取時に利用できる控除制度

iDeCo制度で最も難関なのが
出口戦略です。
iDeCoの受け取り時に使える制度
・退職所得控除
・公的年金等控除
・(障害給付金)
・(死亡一時金)
※障害給付金と死亡一時金は、完全非課税ですが
不慮の事故に巻き込まれるなど
レアケースなので今回は省きます。
一般的には、退職所得控除、
公的年金等控除を利用して受け取ります。
そして、退職所得控除が最も強力です。
退職所得控除の計算式
勤続年数が20年未満の場合
勤続年数※x40万
勤続年数15年なら、600万円が控除限度額。
勤続年数が20年以上の場合
800万円+70万x(勤続年数※-20)
勤続年数39年なら、2,130万円が控除限度額。
※退職金を受け取る際の勤続年数は、
退職金をもらう会社に勤めた年数
※iDeCoのお金を受け取る場合の勤続年数は、
iDeCoの加入年数
退職所得控除でお得に受け取り
60歳でiDeCo、65歳で退職金
これが最もお得な受け取り方です。
モデルケース
Aさん
S社転職年齢:30歳
iDeco加入 :40歳
60歳でiDeCo受け取り
65歳で退職金受け取り
iDeCoの受け取り
退職金控除の計算式
800万円+40万x(20-20)
計算すると控除額は、800万円です。
iDeCoの総積立額が800万円以下なら非課税
退職金の受け取り
退職金控除の計算式
800万円+70万x(35-20)
計算すると控除額は、1850万円です。
退職金が1850万円以下なら、非課税
合計すると2650万円控除されます。
しかし、これが逆だと全く変わります。
60歳で退職金、65歳でiDeCo

60歳で退職金を一括で受取
65歳でiDeCoを一括で受取
この順番は、iDeCoは退職金控除が使えません。
正確に言うと75歳にならないと
退職金控除が使えません。
私も正直納得いきませんが、
制度なので諦めましょう。
モデルケース
Bさん
S社転職年齢:30歳
iDeco加入 :40歳
60歳で退職金受け取り
65歳でiDeCo受け取り
退職金の受け取り
退職金控除の計算式
800万円+40万x(30-20)
計算すると控除額は、1200万円です。
退職金が1200万円以下なら、非課税
iDeCoの受け取り
この場合、公的年金等控除が使えますが
控除限度額は年金含め年間120万円までです。
すると年金額によっては、
全てに課税される可能性があります。
年金がないと仮定しても控除額は、120万円
合計すると1320万円控除されます。
凄まじい減額っぷりです。
75歳まで待つという手もありますが
老後の不安を考えると損な気がします。
分割での受け取りは節税には損

分割で受取る場合は、公的年金控除の対象ですが
年金+iDeCoだと非課税限度額120万円を
超えてしまう可能性が高いです。
私も計算してみましたが、
明らかに退職金控除を利用した方がお得です。
計算式がややこしいので今回は省きます。
▼気になる方は、自分で計算してみましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
60歳未満で一時金が出るのは?
加入者が死亡した場合

例えば夫がiDeCo加入者で60歳になる前に
亡くなった場合は、死亡一時金として
家族に積立金が一括で支給されます。
ただし、受け取るためには
加入者の死亡後5年以内にその支払いを求める
手続きをおこなう必要があります。
そのため、自分が死亡した時の
受取方を家族と共有しておく必要があります。
また、死亡一時金を受取り時には
相続税がかかりますが
法定相続人1人につき500万円まで
非課税となる優遇措置があります。
ここはしっかりと話し合っておきましょう。
加入者が障害を負った場合

事故等で障害を負い、以下の認定を受けた加入者は
iDeCoでの積立金を60歳より前に
受け取ることができます。
・障害基礎年金の受給者(1級および2級)
・身体障害者手帳(1級~3級)の交付者
・療育手帳(重度の者に限る)の交付者
・精神保健福祉手帳(1級および2級)の交付者
死亡一時金と違い、障害給付金の場合は
受取時に課税されません。
さらに一括もしくは分割での受け取りを
選択できるようになります。
障害給付金の受け取りにも手続きが必要です。
もしもの時のために手順を確認しておきましょう。
まとめ

いかがだったでしょうか。
iDeCoは、お得に積み立てられる反面
受取時に考えることが多いですが
ちゃんと整理すれば
お得な受け取り方はシンプルです。
ただ、労働期間が長くなるため
FIREを目指す人は、
ある程度節税面を捨てる覚悟も必要です。
この記事がいいなと思ったら、
以下のボタンをクリック頂けると
筆者が喜びます。
▼ブログランキング

Share this content:

